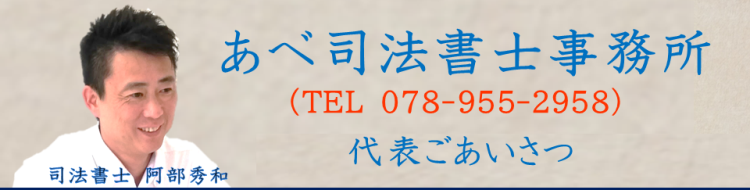不動産の相続
|
|
⽬次 - 不動産の相続(名義変更) |
【 業務のご案内 】
» 手続きの流れ
» 費用のご説明(具体例)
【 ご参考ページ 】
» ご自身で手続きする場合(ご参考)
手続きの流れ(ご相談~登記完了まで) |
||||||||||||||||||||||||||
|
費用のご説明(具体例) |
||||||
|
当事務所は基本的に法定相続人の数と不動産の個数、申請件数を基準に手数料を算定しております。
以下に具体例をご紹介します。 |
| < 登記費用の具体例 > | ||||||||
|
【前提条件】
|
||||||||
| 項 目 | 金 額(円) | 備 考 | ||||||
| 基本手数料 | 60,000 | |||||||
| 相続人数加算 | 16,000 | @8000×【2】 | ||||||
| 不動産個数加算 | 3,000 | 個数が【2】なので3,000円 | ||||||
| 事前調査費用 | (実費) | @332×【2】=664円 | ||||||
| 完了後証明書費用 | (実費) | @500×【2】=1,000円 | ||||||
| 戸籍等取得費 | (実費) | 数千円~ | ||||||
| 登録免許税 | (実費) | 固定資産評価額の0.4% | ||||||
| 合 計 | 79,000円+(実費) | ※ 別途、消費税がかかります。 | ||||||
当事務所の代行サービス |
||||||||||||||||||||||
|
ご相談・ご依頼の方法 |
||||||
|
平⽇/09:00〜19:00 平日/19:00~21:00(要ご予約) ⼟⽇/10:00〜15:00(要ご予約) |
||||||
|
《メールでのご相談ご予約》 メールには、以下の項⽬をお書きください。 ご希望の日時は複数(2〜3つ程度)お書きいただけますと、スムーズです! ① お名前 ② メールアドレス ③ ご希望の日時とご相談内容 |
||||||
|
《 お電話でのご相談ご予約 》 TEL:078-955-2958 (※ 非通知設定はお受けできません。ご了承ください。)
|
» 目次に戻る
名義変更が必要なケース |
|||||||||
|
不動産の「売買」や「贈与」などと違って、「相続」の登記はよく放置されてしまいがちですが、次のような場合は、相続といえども名義変更が必要ですのでご注意ください。 尚、令和6年4月1日からは相続登記申請が義務となります。正当な理由なくこの義務を履行しない場合は、10万円以下の過料が科されることがあります。 |
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
» 目次に戻る
ご自身で手続きする場合 |
||||||||||
|
作業は以下のとおりですが、大変と感じられたらぜひ司法書士にご用命ください。 時間と手間が大幅に節約できます。 TEL 078-955-2958 |
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
» 目次に戻る